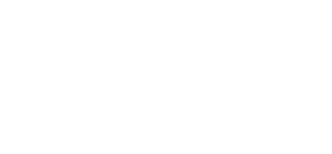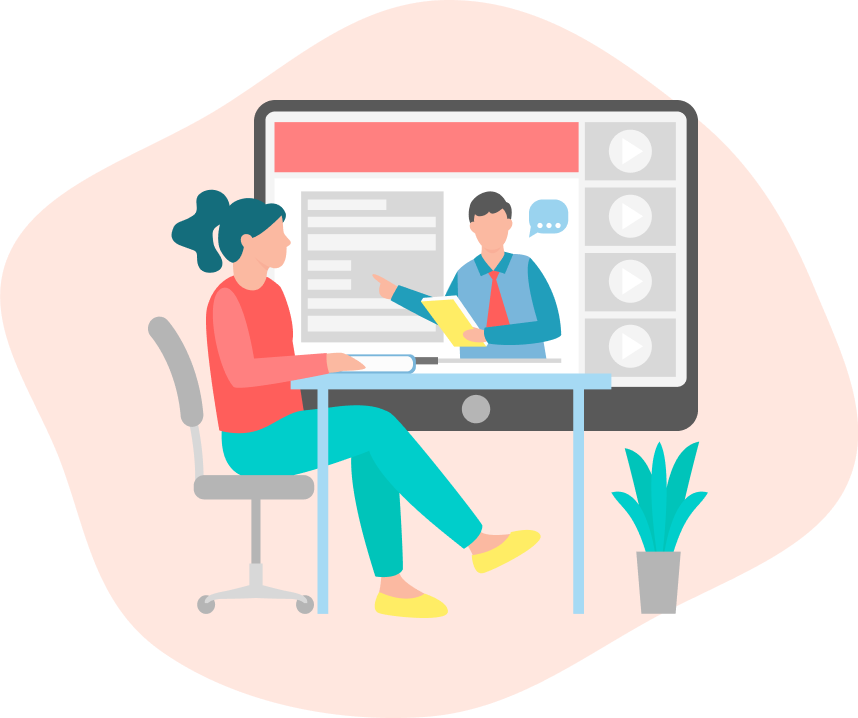BtoB製造業の戦略的なコンテンツ活用を促進するDAM・PIMとは?
- 業界アプローチ

製造業におけるデジタル変革(DX)は、製品や工程の改善だけにとどまりません。今、企業価値を高める上で欠かせないのが、製品にまつわる情報や販促コンテンツをいかに整理し、戦略的に活用するかという視点です。特にBtoB製造業では、製品情報が複雑化し、多拠点展開や海外対応なども加わる中で、情報の分断や属人化が大きな課題になっています。正しい情報が必要な人に届かない、あるいは更新が追いつかないといった状態は、営業機会の損失や非効率を引き起こし、企業全体の成長にブレーキをかけかねません。
本記事では、こうした課題を乗り越える鍵となる「DAM(デジタルアセット管理)」と「PIM(商品情報管理)」の役割に注目し、情報活用がいかに経営戦略の中核になりうるかを解説していきます。
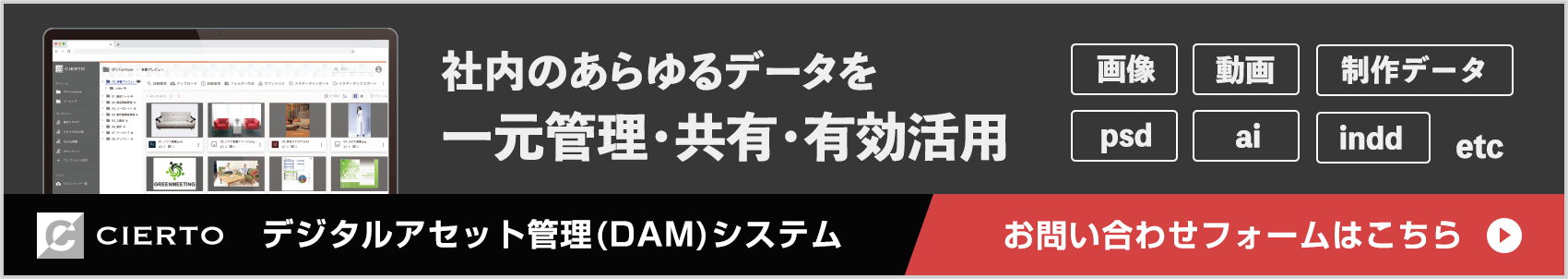
1. なぜ、今「情報の使い方」が経営課題なのか
1-1. BtoB企業こそ情報戦略が武器になる
BtoB製造業では、製品の構造が複雑で仕様も多岐にわたるため、営業や販促に必要な情報量は非常に多くなります。顧客に正確な仕様を伝えるためには、図面や写真、製品ごとのスペック、使用例、導入事例など多種多様な情報を組み合わせて提示する必要があります。そしてその情報の質やスピードが、営業成果や顧客満足に直結します。しかし実際には、情報の所在が部署や担当者によって異なっていたり、更新されていない古い資料が流通していたりすることが珍しくありません。営業担当が「どれが最新版かわからない」と悩みながら過去の資料を使い回したり、マーケティング部門がコンテンツ制作のたびに同じ素材を探し直したりする非効率は、多くの企業で日常的に発生しています。
グローバルに展開している企業であれば、さらに多言語対応やローカライズの手間がかかり、情報共有の難易度は一層高まります。こうした中で、情報がバラバラに管理されている状況は、ただの業務課題ではなく、企業競争力の低下に直結する経営課題と捉えるべきです。
1-2. 「管理」ではなく「戦略的活用」へ
これまで多くの企業では、情報の整備や管理は「現場の工夫」や「担当者の努力」に委ねられてきました。しかし現在のビジネス環境では、それだけでは限界が来ています。製品ライフサイクルが短くなり、情報の更新頻度が増す中で、情報をいかに効率よく、正確に、そして柔軟に活用できるかが問われています。単に情報を保管するだけの仕組みではなく、それらを社内外のさまざまなチャネルやチームで活用できる状態をつくること。すなわち「戦略的に使いこなせる情報基盤」を整えることが、今後の製造業にとって不可欠な投資領域となっています。
2. 現場で起きている「情報の混乱」と見えづらい課題
2-1. 担当者任せの管理が生む属人化と非効率
製品情報やコンテンツが、特定の担当者の知識や経験に頼って管理されている状態は、長年の業務習慣の中で半ば当然のものとして定着しています。しかし、それは情報が「引き出せる人にしか引き出せない」状態であることを意味し、誰かが休職・退職するたびに情報がブラックボックス化するリスクを抱えています。
さらに、情報の所在が明確でなければ、必要な資料を探すために毎回人に聞く、同じ作業を繰り返すといった非効率が発生します。これらは日々の現場では“仕方のないこと”として黙認されがちですが、実際には無駄な時間・労力・ミスを生み出し、企業全体の生産性を静かに下げているのです。
2-2. コンテンツの重複制作がコストと時間を浪費する
製品情報に紐づく画像・動画・カタログ・提案資料などのコンテンツは、本来であれば資産として再利用されるべきものです。しかし、これらの素材がどこにあるのか分からない、どれが最新なのか判別できないという理由から、既にある情報を再度一から作り直している現場が少なくありません。
このような“無意識の重複制作”は、社内外での制作コストやコミュニケーションコストを押し上げるだけでなく、本来注力すべきクリエイティブや戦略的業務に時間を割けない要因にもなります。経営者の視点から見ると、目に見えない「隠れコスト」として、販促や営業効率に深刻な影響を与えていることを見落としてはなりません。
2-3. 情報の混乱は経営層に“見えないコスト”として積み上がる
製品情報やコンテンツが現場でうまく活用できていないにもかかわらず、日常的に起きている非効率や混乱は、経営層には“問題”として上がってこないことがほとんどです。理由は明快で、業務としてはなんとか回ってしまっているからです。ミスがあっても現場でリカバリーされ、時間がかかっても「そういうものだ」と認識されている――つまり、問題が問題として顕在化していないのです。
しかしその裏では、営業機会の損失、顧客満足度の低下、社員のモチベーションの低下といった、見えない損失が日々積み重なっています。これらは短期的には目立ちませんが、長期的には企業の競争力を確実に削ぐ、じわじわと効いてくる経営リスクです。
2-4. 多拠点・グローバル展開でさらに広がる情報ギャップ
国内外に拠点や代理店を展開している製造業にとっては、製品情報やコンテンツの整合性を保つ難易度がさらに高くなります。たとえば、本社と海外支社で製品の仕様や価格、名称表記が異なる、拠点ごとに独自の販促資料が作られてブランドトーンがばらついている――こうした状態は、“見た目はきれいだが中身が揃っていない”情報流通を生み出します。
このギャップを埋めるために、各拠点で翻訳や資料制作をやり直すといった無駄な二度手間が発生し、現地の営業力やブランド訴求力も弱まります。グローバル戦略を成功させるためには、まず情報基盤を本社主導で整備し、どこでも同じ品質の情報が使える状態を作ることが不可欠なのです。
3. なぜ今、DAMとPIMの融合が注目されているのか
3-1. 既存の情報管理では限界がある
製造業の多くは、ERPやPLMといった業務系のシステムを導入し、生産や在庫、品質管理などをデジタル化してきました。しかし、こうしたシステムは「工場を動かすための情報管理」には強い一方で、製品を“売る”ための情報――つまり、営業やマーケティング、販促活動で活用される製品情報やコンテンツの管理には対応しきれていないのが実情です。
特にBtoB製造業では、営業提案資料やカタログ、商品画像、説明動画など、コンテンツの量と種類が非常に多岐にわたります。それらが社内のサーバや個人フォルダに散在し、ファイル名や更新履歴も不明なまま扱われているケースも少なくありません。海外拠点や複数部署での展開が進むほど、情報はより複雑に絡み合い、管理コストと運用負担は増加していきます。
情報が多ければ多いほど、本来は“活用のチャンス”が広がるはずです。しかし、整理されていなければ、その情報はむしろ混乱の原因となり、逆に業務を圧迫してしまいます。既存のシステムや人の努力だけでは、もはや情報管理の限界が見え始めているのです。
3-2. DAMとPIM、それぞれの役割と特長
こうした課題を解決するために導入が進んでいるのが、「DAM(Digital Asset Management)」と「PIM(Product Information Management)」です。それぞれの役割は明確に異なりますが、いずれも“製品を正しく伝える”ための情報管理基盤として機能します。
DAMは、画像や動画、PDFなどの非構造データ、いわゆる“デジタルアセット”を一元的に管理する仕組みです。誰が・いつ・何のために使ったのかという利用履歴も記録され、社内外の関係者と適切なバージョンを安全に共有することができます。一方、PIMは製品名、型番、サイズ、価格、素材、対応国といった商品マスタ情報を一元化・構造化するための仕組みで、多言語対応やチャネル別出力にも強みを発揮します。
この二つのシステムは、単体でも十分に価値がありますが、連携させて運用することで初めて、製品情報とコンテンツを結びつけた“使える情報基盤”が完成します。たとえばPIMで管理された製品情報に対して、対応する画像やカタログPDF、動画などをDAM経由でひも付ければ、商品を軸とした包括的なコンテンツ活用が可能になります。
3-3. 情報管理から“戦略的活用”へ
DAMとPIMを組み合わせた情報基盤の最大の価値は、「活用」前提で情報を整えられる点にあります。ただ蓄積するのではなく、必要な情報を、必要なタイミングで、必要な人が、迷わず使える状態――それこそが、戦略的な情報運用の理想形です。
また、こうした構造化された情報環境は、AIや自動化ツールとの親和性も高くなります。たとえば、PIMに登録された商品スペックをもとに、AIがカタログ原稿や商品説明文を自動生成したり、DAM内の画像や動画と連動してECページの更新を効率化したりといった、新たな活用の幅が広がります。
特定の担当者に依存せず、誰でも正しい情報にアクセスし、それをベースに顧客への提案や販促活動を展開できる環境は、もはや“業務改善”ではなく、“企業戦略”そのものです。デジタル資産を、眠らせるのではなく売上につなげる。その実現に向けて、今こそDAMとPIMの融合が注目されているのです。
4. BtoB製造業における、DAM×PIM導入の具体的な効果とは?
DAMとPIMの導入によって、製造業の情報活用にどのような変化が生まれるのか。それは単なる業務改善にとどまらず、営業スピードの向上や海外拠点との連携強化、AI導入の土台づくりといった経営的なインパクトにまで広がります。ここではその代表的な効果を4つの観点から整理していきます。
■営業・販促スピードの大幅向上
まず最も直接的な効果は、営業や販促業務のスピードが飛躍的に向上することです。DAMとPIMの導入によって、製品に関する最新情報や関連コンテンツがひとつの基盤上で整理され、誰もが迷うことなくアクセスできるようになります。営業担当者が製品カタログや提案資料を作成する際も、正確で最新の情報とビジュアル素材がすぐに揃うため、資料作成や社内確認の時間を大幅に短縮することができます。
資料探しや手戻りにかけていた時間がなくなれば、その分を顧客との商談や新規案件開拓に振り向けられ、結果として売上や受注率の向上にもつながります。
■グローバル展開・多拠点対応の効率化
多言語対応や多拠点展開においても、DAMとPIMの組み合わせは非常に有効です。PIMでは製品情報を構造的に管理できるため、言語ごとの表記ルールや通貨、単位などを柔軟に切り替えて対応することが可能になります。そして、対応するコンテンツもDAM上で紐づいて管理されるため、各国・各拠点においても整合性の取れた販促資料や営業支援コンテンツを展開することができます。
これにより、海外代理店や販売パートナーとの情報共有もスムーズになり、ローカライズのスピードと正確さが飛躍的に高まります。情報のばらつきによる誤認識やブランドの一貫性の欠如といったリスクも、大きく軽減されます。
■属人化の解消と業務標準化
DAMとPIMの導入は、情報の属人化を防ぎ、業務の標準化を推進するうえでも効果的です。これまで「〇〇さんしかわからない」「〇〇課に聞かないと出てこない」といった状態で運用されていた情報が、システム上に明確なルールと構造で整理されることにより、誰が見ても理解でき、使える状態に変わります。
これにより、特定の社員の知識やノウハウに依存するリスクが下がり、人の入れ替わりや部署異動があっても業務の質を維持しやすくなります。また、新人教育やマニュアル整備も効率化され、企業全体の情報リテラシーが底上げされるという副次的な効果も期待できます。
■AI・自動化との親和性の高さ
近年注目されているAIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との連携においても、DAMとPIMはその土台として欠かせない存在です。なぜなら、AIによる自動生成やレコメンドを行うには、整備された構造化データと、それに紐づく高品質なコンテンツという“燃料”が必要だからです。
たとえば、PIMに登録された製品仕様をもとに、AIが商品説明文やEC向けコピーを自動生成する。あるいは、DAMに蓄積された画像や動画を用いて、提案資料やカタログのレイアウトを自動で組み上げる。こうした活用は、すでに実現可能な領域に入りつつあります。
AIを“賢く使う”ためには、まず“情報の整備”が欠かせません。DAMとPIMは、そのための前提条件を整える役割を果たすのです。
5. 経営者が今考えるべき、情報活用の投資戦略とは
製造業におけるデジタル化の取り組みは、これまで設備投資や製造プロセスの効率化を中心に進められてきました。しかし、これからの時代において経営者が注視すべき投資先は、現場の機械ではなく「情報」そのものです。製品を“売る”ための情報、顧客に“伝える”ための情報、そして企業のブランドを“築く”ための情報──これらをどのように整備し、どう活かしていくかが、競争力の核心になろうとしています。
従来、多くの企業において情報整備はコストとみなされがちでした。「属人化していても何とか現場が回っている」「情報が点在していても、部門ごとの工夫で対応できている」という感覚が残っている企業も少なくありません。しかしそのような状態は、裏を返せば「機会損失に気づいていない」状態でもあります。情報の混乱によって失われている商談のスピード、コンテンツ制作の重複、海外展開時のコミュニケーションロス──これらはすべて、見えづらいコストとして経営に重くのしかかっているのです。
今、情報活用の整備は“守り”ではなく“攻め”の投資と捉えるべきフェーズに入っています。営業やマーケティングの生産性を高め、ブランド価値を維持・強化し、AIや自動化の可能性を引き出すための土台として、情報基盤への投資は企業成長に直結する経営戦略といえるでしょう。
その際、重要なのは単にシステムを導入することではなく、「何のために情報を整えるのか」「誰がどのように使うのか」といった視点をもって取り組むことです。現場任せではなく、経営層が主導して情報活用のビジョンを描き、それに即した体制・ルール・ツールを整備していくことが、最終的に全社的な成果につながっていきます。
製品や価格での差別化が難しくなる中、企業としての強みをどう構築していくかが問われています。今こそ、情報を“資産”として扱い、活用を前提とした整備に本気で取り組むタイミングです。DAMとPIMはその第一歩であり、そこから広がる可能性は決して小さくありません。
6. まとめ:情報活用の基盤として「CIERTO」が果たす役割とは
デジタル変革(DX)の本質は、単なるテクノロジー導入ではなく、企業が自らの情報資産をどう扱い、どう活かしていくかという文化と仕組みの転換にあります。製品情報や販促コンテンツを正しく整備し、それらを誰もが使える状態にすることこそが、製造業におけるDXの出発点です。そうした変革を現実のものとするには、ツール選定も重要な経営判断のひとつです。私たちVPJが提供するCIERTO(シェルト)は、DAMとPIMの機能を兼ね備えた“統合型情報マネジメントシステム”として、製造業の複雑な製品情報とコンテンツ活用を一気通貫で支えることができます。
CIERTOは、画像・動画・PDFなどのあらゆるコンテンツを一元管理するDAM機能に加え、製品情報を構造的に整理・運用できるPIM機能を統合しており、製品情報と販促素材の連携を自動化・標準化できます。これにより、営業資料や販促物の整備、海外展開時の多言語対応、AIを活用したコンテンツ生成など、さまざまな業務領域における“情報活用力”を高めることが可能になります。
実際にCIERTOを導入した製造業のお客様からは、「営業資料作成にかかる時間が半分以下になった」「代理店への情報共有が格段にスムーズになった」といった声が多数寄せられています。DXの第一歩をどこから始めるべきか悩まれている企業こそ、まずは自社の情報資産を戦略的に整える環境から着手されることをおすすめします。
製品情報とコンテンツは、企業にとって“見えづらいが確かな資産”です。CIERTOは、その資産価値を最大化し、貴社のビジネスを次のステージへ導く力となるでしょう。CIERTOに関する詳細の紹介は、こちらのCIERTO製品サイトもしくは資料ダウンロードよりご確認ください。
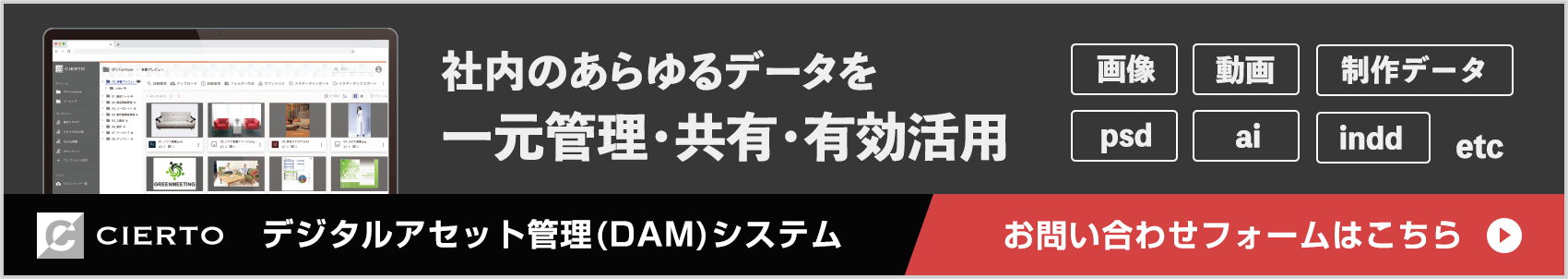
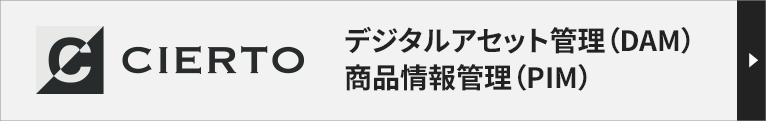
-

-
執筆者情報
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部です。マーケティングや商品、コンテンツ管理業務の効率化等について詳しく解説します。
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン について】
デジタルアセットマネジメント(DAM)を中核に、多様化するメディア(媒体)・コンテンツの制作・管理・配信環境を支援するITソリューションをご提案しています。