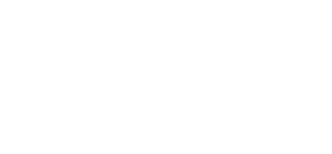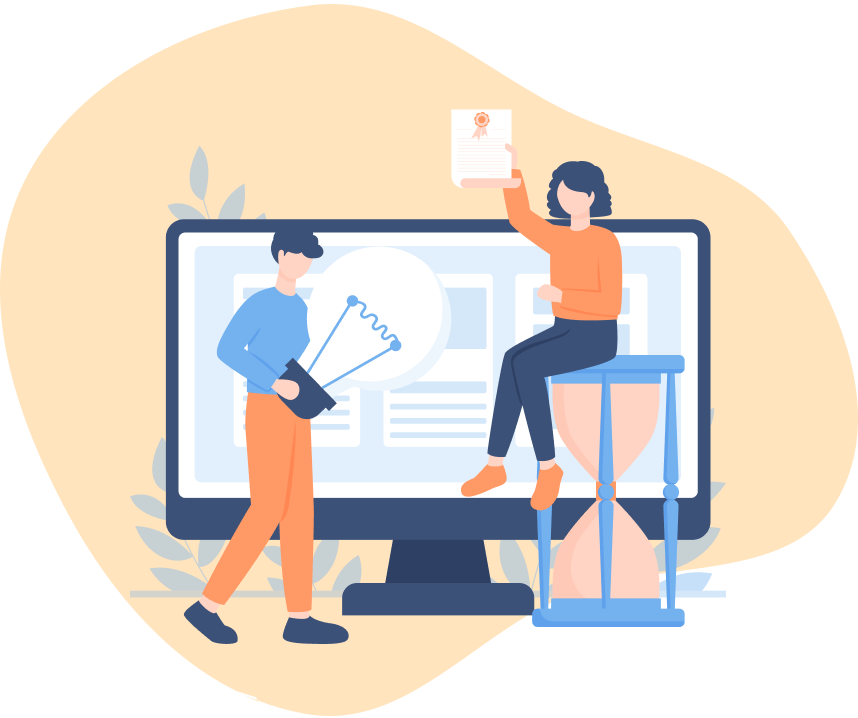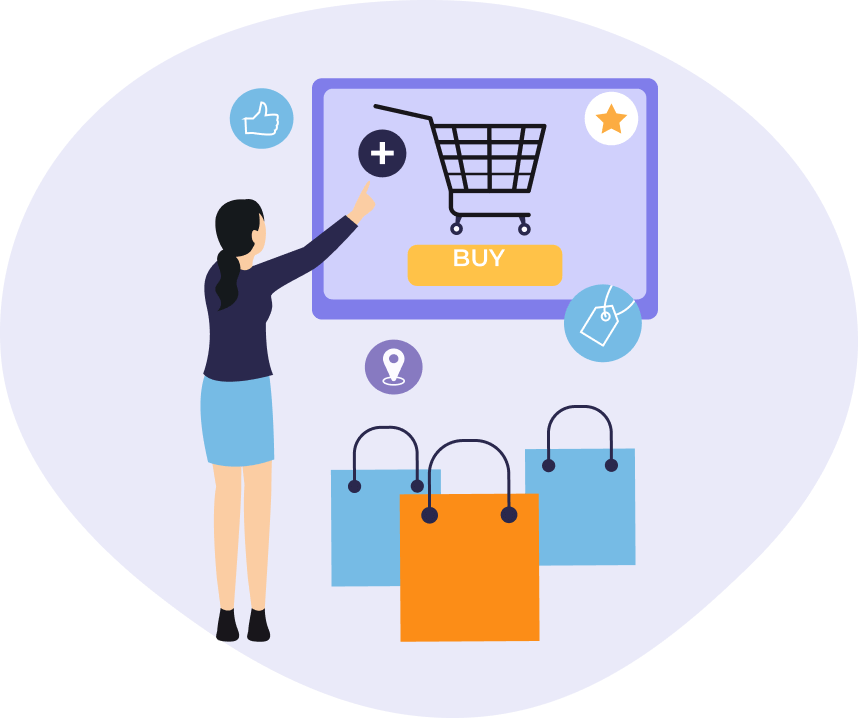PDM(製品情報管理)システムとは?導入メリットやPLMとの違い、活用方法を解説
- データ一元管理
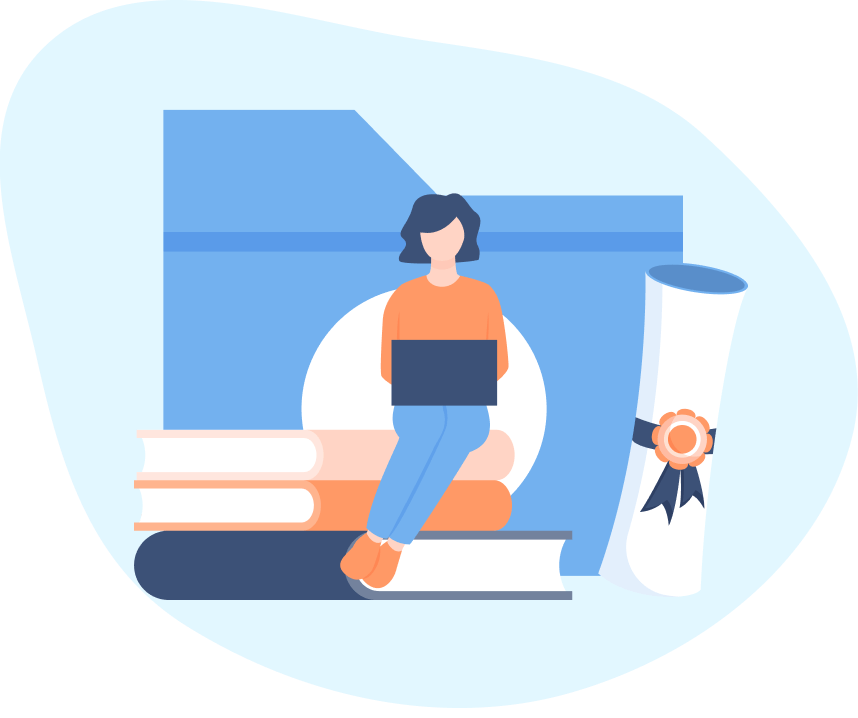
PDM(製品情報管理)システムは、製造業における製品開発プロセスの効率化と品質向上を実現する重要なツールです。現代の製造業では、製品の高機能化・多品種化が進み、設計段階で扱う情報量が膨大になっています。CADデータ、BOM(部品表)、設計図面、仕様書など、従来の手作業による管理では限界があった複雑な製品情報を、PDMシステムが一元管理することで、データの整合性確保と効率的な情報共有を実現します。
本コラムでは、PDMシステムが製造業を中心に導入されている背景から、データ管理・検索・セキュリティなどの主要機能、導入によるメリット、そしてPLMやPIMなど類似システムとの違いまで詳しく解説します。
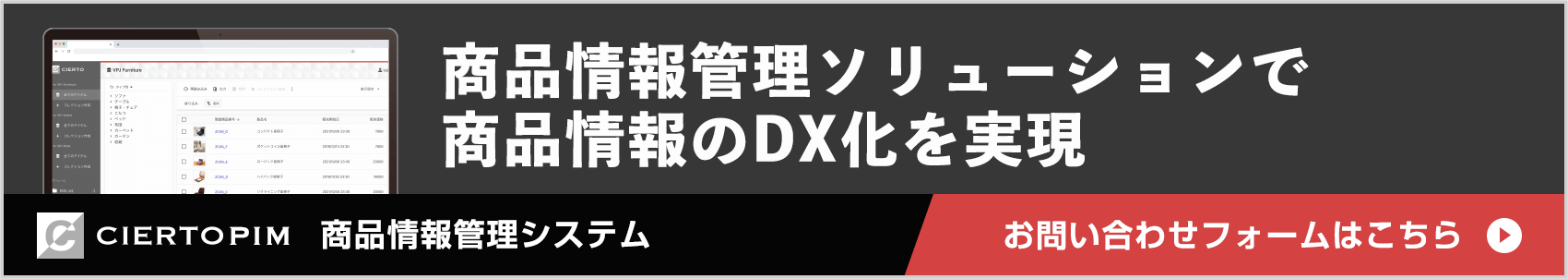
1.PDM(製品情報管理)とは?
PDM(製品情報管理)とは、製品の設計から製造までの情報を一元管理するシステムです。利用部門としては、製品企画部門、設計部門、製造部門、技術部門など、製品製造プロセスに関わる部門となります。製造プロセスにおいては、設計図面や仕様書、指示書、部品表、製造工程表など製品製造に関わる様々な情報で溢れています。これらの製品情報を一元管理し、製品データの整合性を保つことで、円滑な情報共有と業務効率化、品質向上を図ることが可能です。
設計部門では、設計図面や仕様書などのデータを一元管理し、バージョン管理や変更履歴の追跡が可能です。これにより、最新の設計情報を常に利用できるため、設計ミスの防止や効率的な作業が実現します。製造部門では、PDMを通じて設計部門からの情報を正確に受け取り、製造計画や工程管理を行います。情報の一元管理により、製造プロセスの透明性が向上し、トラブルの早期発見・対応が可能になります。
さらに、品質管理部門や購買部門でもPDMを利用することで、製品に関する情報を一元的に管理し、品質向上やコスト削減に貢献します。全ての関連部署が最新の情報を共有することで、企業全体の業務効率が向上し、競争力を強化することができます。 PDMは、企業の製品開発プロセスを支える重要なツールであり、効率的なデータ管理と情報共有を実現するために不可欠なシステムです。
従来の手作業による管理やExcelでの管理では、データの重複、断片化、紛失が頻発し、最新バージョンの確認や変更履歴の追跡が困難な状況が生まれていました。特に、複数部門で同じデータが別々に管理され、異なるバージョンや管理番号が付与されることで、製造現場での混乱や品質問題が発生するリスクが高まっていました。また、グローバル化により海外拠点との情報共有が必要となり、時差やコミュニケーションの課題も加わって、情報管理の複雑さは増す一方です。
これらの課題を解決し、競争力を維持・向上させるため、製造業を中心にPDMシステムの導入が積極的に推進されています。
1.1 PDM(製品情報管理)の役割について
PDMは、企業の製品開発プロセスを支える重要なツールであり、効率的なデータ管理と情報共有を実現するために不可欠なシステムです。製品データの整合性を保ち、情報共有を円滑にすることで、業務の効率化と品質向上を図ります。設計部門では、設計図面や仕様書などのデータを一元管理し、バージョン管理や変更履歴の追跡が可能です。これにより、最新の設計情報を常に利用できるため、設計ミスの防止や効率的な作業が実現します。製造部門では、PDMを通じて設計部門からの情報を正確に受け取り、製造計画や工程管理を行います。情報の一元管理により、製造プロセスの透明性が向上し、トラブルの早期発見・対応が可能になります。
さらに、品質管理部門や購買部門でもPDMを利用することで、製品に関する情報を一元的に管理し、品質向上やコスト削減に貢献します。全ての関連部署が最新の情報を共有することで、企業全体の業務効率が向上し、競争力を強化することができます。 PDMは、企業の製品開発プロセスを支える重要なツールであり、効率的なデータ管理と情報共有を実現するために不可欠なシステムです。
1.2 PDMシステムが製造業を中心に導入されている背景
現代の製造業では、製品の高機能化や多品種化が急速に進み、設計段階で扱う情報量が膨大になっています。CADデータ、BOM(部品表)、仕様書、図面、シミュレーション結果、製造指示書、試験結果など、一つの製品開発に関わる情報は多岐にわたり、その数は数万から数十万のファイルに及ぶこともあります。従来の手作業による管理やExcelでの管理では、データの重複、断片化、紛失が頻発し、最新バージョンの確認や変更履歴の追跡が困難な状況が生まれていました。特に、複数部門で同じデータが別々に管理され、異なるバージョンや管理番号が付与されることで、製造現場での混乱や品質問題が発生するリスクが高まっていました。また、グローバル化により海外拠点との情報共有が必要となり、時差やコミュニケーションの課題も加わって、情報管理の複雑さは増す一方です。
これらの課題を解決し、競争力を維持・向上させるため、製造業を中心にPDMシステムの導入が積極的に推進されています。
2. PDMシステムの主要機能
PDMシステムは、製品情報を一元管理し、設計から製造までのプロセスを効率化するための様々な機能を提供します。ここでは、主な機能について詳しく見ていきます。
2.1 データ管理機能
PDMシステムの中核を成すのがデータ管理機能です。設計図面、仕様書、部品リスト(BOM)など、膨大な量のデータを効率よく整理し、必要な情報を迅速に検索できるようにします。また、データのバージョン管理機能を備えており、変更履歴を追跡することで、常に最新の情報を維持することが可能です。2.2 ワークフロー管理機能
ワークフロー管理機能は、設計から製造までのプロセスを自動化し、効率化を図るための機能です。これにより、各工程の進捗状況をリアルタイムで把握し、タスクの遅延やボトルネックを早期に発見することができます。さらに、承認プロセスの自動化により、関係者間のコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにします。ワークフローの標準化により、業務プロセスの品質を向上させることもできます。2.3 統合機能
PDMシステムは、CADやERPなど他のシステムと連携する統合機能を備えています。特にCAE(構造解析システム)、CAM(加工工程設計システム)、PLM(製品ライフサイクル管理システム)との連携により、設計から製造までの情報の一貫性を確保し、データの整合性を保ちながら効率的な製品開発を実現します。2.4 データ検索・再利用機能
PDMシステムは、キーワード検索や3D形状による類似部品検索など、多様な検索方法により過去の設計データを迅速に特定できます。これにより既存の設計資産を有効活用し、設計期間の短縮とコスト削減を実現します。2.5 セキュリティ機能
PDMシステムは、企業の重要な知的財産である設計情報を保護するため、堅牢なセキュリティ機能を提供します。ユーザーの役割や所属部門に応じたアクセス権限の設定により、機密情報への不正なアクセスを防止します。また、データの閲覧、編集、削除などの操作ごとに細かな権限制御が可能で、プロジェクトの段階に応じて適切な情報公開レベルを維持できます。操作履歴の記録・追跡機能により、セキュリティインシデントの早期発見と対応を支援し、内部・外部脅威から企業の重要データを保護します。3. PDMシステムの導入メリット
PDMシステムを導入することで、多くのメリットを享受することができます。ここでは、主要な導入メリットについて説明します。
3.1 正確な情報へのアクセス
PDMシステムは、製品に関する全てのデータを一元的に管理することができます。これにより、情報の整合性を保ち、重複やミスを防止します。また、データの検索やアクセスが容易になるため、業務効率が向上します。さらに、アクセス権の設定により、情報のセキュリティを確保することも可能です。3.2 設計の効率化
設計プロセスの効率化も、PDMシステム導入の大きなメリットです。設計データの一元管理により、必要な情報を迅速に取得できるため、設計の手戻りを減少させることができます。また、CADシステムとの統合により、設計変更が即座に反映されるため、エラーの発生を抑制することができます。3.3 コラボレーションの強化
PDMシステムは、複数の部門やチーム間でのコラボレーションを強化します。情報の一元管理により、関係者全員が最新の情報にアクセスできるため、コミュニケーションが円滑になります。また、ワークフロー管理機能により、タスクの進捗状況をリアルタイムで把握することができ、プロジェクトのスムーズな進行が可能です。3.4 品質管理の向上
品質管理の向上も、PDMシステムの導入メリットの一つです。データの一元管理により、品質に関する情報を迅速に取得できるため、問題の早期発見・対応が可能です。また、レポートと分析機能により、品質管理の状況を可視化し、改善点を特定することができます。3.5 コスト削減
PDMシステムの導入により、コスト削減も期待できます。情報の一元管理により、データの重複やミスが減少し、業務効率が向上するため、コストの削減が可能です。また、設計プロセスの効率化やエラーの発生抑制により、無駄なコストを削減することができます。4. PDMシステム導入の注意点
4.1 業務プロセスとの整合性
PDMシステムを導入する際には、既存の業務プロセスとの整合性を確保することが重要です。PDMの導入は、新しい技術やシステムを取り入れることを意味し、これにより業務フローやプロセスが大きく変わる可能性があります。例えば、設計から製造までのデータ管理や情報共有の方法が一新されることで、従来の手作業によるプロセスが自動化されることがあります。これにより、業務の効率化が図られる一方で、既存の業務プロセスとの不整合が生じることも考えられます。このような変化をスムーズに進めるためには、PDMシステム導入前に現行の業務プロセスを詳細に分析し、新しいシステムに適応するためのプロセス改善を行う必要があります。具体的には、業務フローの見直しやタスクの再配置、関係者間のコミュニケーションの強化などが求められます。また、業務プロセスの変更による影響を最小限に抑えるために、段階的なシステム導入やパイロットプロジェクトの実施が有効です。
さらに、業務プロセスとPDMシステムの整合性を確保するためには、経営層や管理者の理解と協力が欠かせません。トップダウンでの推進とともに、現場の声を反映させたボトムアップのアプローチが重要です。これにより、全社的な理解と協力を得て、システム導入を成功に導くことができます。
4.2 ユーザー教育とサポート
PDMシステムの効果的な活用には、ユーザー教育とサポートが不可欠です。新しいシステムに適応するためには、ユーザーがシステムの操作方法や機能を十分に理解し、日常業務に活用できるようになることが重要です。そのため、PDMシステムを選定する際は、導入時のオンボーディング支援が行われるか、導入後のサポート体制が整っているかを確認し、ベンダーを選定しましょう。ユーザー教育については、システム導入時はもちろん、導入後についても継続的な研修会やフォローアップを通じて、新機能やアップデート情報を提供し、ユーザーが常に最新の知識を持ち続けるような支援が重要となります。
また、サポート体制の整備も欠かせません。問題に直面した際に迅速に対応できる専用のサポートデスクやヘルプラインなど、専門スタッフが求められます。さらに、FAQの整備やオンラインサポートの提供など、多様なサポートチャネルを用意することで、問題を迅速かつ効果的に解決することができます。
これらの取り組みにより、ユーザーがPDMシステムを最大限に活用し、業務効率や生産性の向上を実現することができます。
5.PLMやその他の類似サービスとの違い
5.1 PDMとPLMの違いとは
PDMとPLMは、共に製品開発プロセスをサポートするシステムですが、その範囲と目的において明確な違いがあります。PDMが主に製品の設計や製造フェーズに向けたソリューションであるのに対し、PLMは、製品の設計、製造、販売、アフターサービス、廃棄まで全てのフェーズをカバーし、製品のライフサイクル全体を管理する目的のシステムになります。PLMは、企業全体のプロセスを統合し、情報の流れを管理することで、製品の品質向上や市場投入までの時間短縮、コスト削減を実現します。具体的には以下のような機能を持ちます。PLM(製品ライフサイクル管理)
- ライフサイクル管理:製品の全ライフサイクルを通じてデータを管理し、各フェーズの情報を統合。
- プロセス統合:設計、製造、販売、サービスなど、異なる部門間のプロセスを統合し、効率化を図る。
- コラボレーション支援:グローバルなチーム間でのコラボレーションを支援し、情報共有とコミュニケーションを強化。
5.2 その他の類似サービスとそれぞれの位置づけ
製品情報を管理する類似サービスとして、PIM(製品情報管理)とMDM(マスターデータ管理)があります。それぞれデータ管理における重要なサービスですが、その目的と適用範囲には明確な違いがあります。詳しくは、こちらのコラム「製品情報管理の全貌:PDM、PLM、PIM、MDMの違いとは」にも記載しておりますので、ご興味ある方は参考にしてください。PIM(製品情報管理)
PIMは、製品に関連する情報を一元管理するシステムです。製品仕様、画像、説明、価格情報など、マーケティングや販売に必要なあらゆるデータを統合し、管理します。PIMは特にeコマースや小売業において、製品情報の一貫性と正確性を保つために使用され、各チャネルへの迅速なデータ配信を支援します。これにより、顧客への情報提供の質が向上し、販売機会を最大化することができます。
MDM(マスターデータ管理)
MDMは、企業全体の基幹データ(マスターデータ)を統合・管理するシステムです。製品情報や顧客情報、サプライヤー情報、従業員情報などマスターデータとして一元管理し、データの整合性と品質を確保します。MDMは異なるシステムやアプリケーション間で一貫したデータを提供し、業務全体の効率化と正確な分析を実現します。これにより、企業全体の運用効率が向上し、データに基づく戦略的意思決定が可能になります。
6.PDMとPLM、MDM、PIMの違いとは
6.1 PDMとMDMの違い
MDM(マスターデータ管理)は、企業全体の基幹データ(マスターデータ)を統合・管理するシステムです。製品情報、顧客情報、サプライヤー情報、従業員情報などを一元管理し、データの整合性と品質を確保します。PDMが製品の設計・開発段階のデータ管理に特化しているのに対し、MDMは異なるシステムやアプリケーション間で一貫したデータを提供し、業務全体の効率化と正確な分析を実現します。これにより、企業全体の運用効率が向上し、データに基づく戦略的意思決定が可能になります。6.2 PDMとPIMの違い
PIM(製品情報管理)は、製品に関連する情報を一元管理するシステムで、特にマーケティングや販売に重点を置いています。製品仕様、画像、説明、価格情報など、顧客向けの製品情報を統合管理し、eコマースサイトやカタログ、営業資料など各チャネルへの迅速なデータ配信を支援します。PDMが設計・製造段階の技術的なデータ管理を目的とするのに対し、PIMは販売・マーケティング段階での製品情報の一貫性と正確性を保つことに特化しています。これにより、顧客への情報提供の質が向上し、販売機会を最大化することができます。現代のオムニチャネル戦略において、PIMは製品情報の統一的な管理と配信を実現する重要なソリューションとして注目されています。それぞれのシステムの役割の違いについては、こちらの記事:PDM、PLM、PIM、MDMの違いとは?製品情報管理の全貌を解説で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
7.PIMソリューション「CIERTO」とは
PIMは、製品仕様、カタログ情報、画像や動画といったマーケティング素材までを統合管理し、社内外のあらゆるチャネルへ正確かつスピーディに展開する仕組みです。つまり、PDMが「ものづくりの効率化」を支えるのに対し、PIMは「市場への情報発信力」を高める役割を担います。CIERTO PIMは、商品情報を一元管理し、各種チャネルでの活用を効率化するためのソリューションです。商品名や仕様、価格、説明文、SKU、画像、翻訳データなど、製品に関わるさまざまな情報を集約・管理することで、業務の効率化と顧客体験の向上を実現します。
VPJが提供する CIERTO PIM は、製造業から小売業まで幅広い業界で導入されている先進的なPIMソリューションです。特徴は以下の通りです。
PDMで整備した製品情報をPIMへと拡張し、設計から販売・マーケティングまでをシームレスにつなげることで、企業は製品価値を最大限に発揮できます。CIERTO PIMは、その実現を強力に支援するソリューションです。
CIERTO製品ページ
VPJが提供する CIERTO PIM は、製造業から小売業まで幅広い業界で導入されている先進的なPIMソリューションです。特徴は以下の通りです。
- 製品情報の一元管理:設計データやERP情報と連携し、最新の製品データを常に活用可能。
- マルチチャネル展開:ECや販促物など、必要なフォーマットに自動変換して迅速に配信。
- DAMとの統合:画像・動画などのデジタルアセットも連携管理し、ブランド一貫性を確保。
PDMで整備した製品情報をPIMへと拡張し、設計から販売・マーケティングまでをシームレスにつなげることで、企業は製品価値を最大限に発揮できます。CIERTO PIMは、その実現を強力に支援するソリューションです。
CIERTO製品ページ
まとめ
PDMは、製品の製造プロセスにおける情報管理を実現し、業務効率化や品質向上など多くのメリットをもたらします。また、類似のサービスもあることから、自社の課題やニーズを明確にし要件にあったシステムや製品を選定することが重要となります。
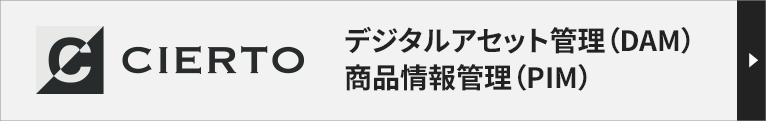
-

-
執筆者情報
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部です。マーケティングや商品、コンテンツ管理業務の効率化等について詳しく解説します。
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン について】
デジタルアセットマネジメント(DAM)を中核に、多様化するメディア(媒体)・コンテンツの制作・管理・配信環境を支援するITソリューションをご提案しています。