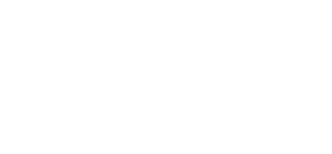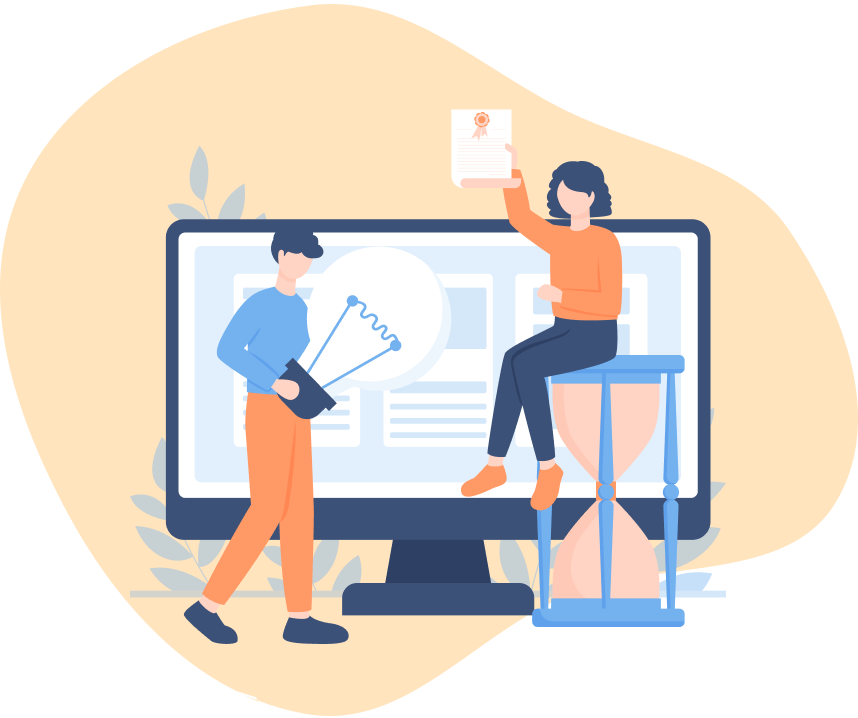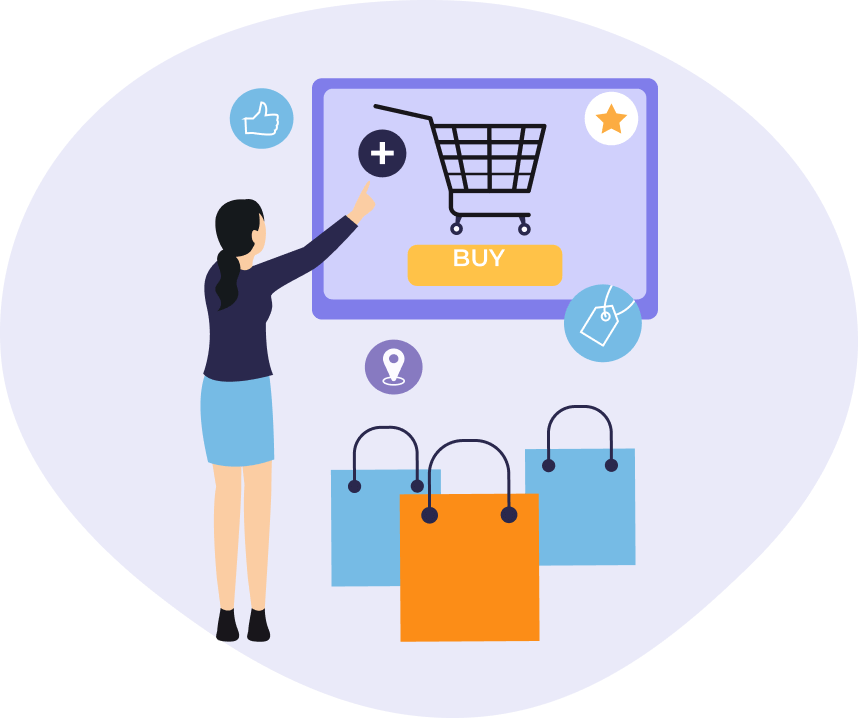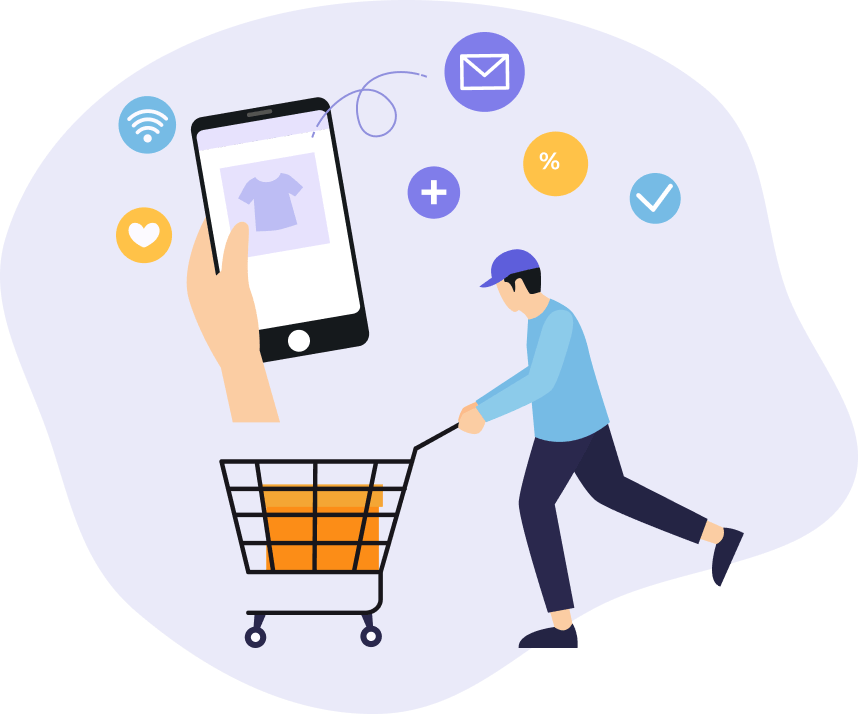なぜ“データ品質”が売上を左右するのか?企業成長に不可欠なデータガバナンス戦略とは
- 顧客体験・データ品質

企業のデジタルシフトが加速し、マーケティングや営業、商品企画においても「データ活用」が不可欠な時代となっています。しかし、その前提となる“データの品質”に本格的に向き合っている企業は、意外にも少ないのが現実です。
どれほど高度な分析ツールやAIを導入しても、ベースとなるデータが誤っていれば、導き出される結果も誤ります。これは、顧客体験の低下や売上機会の損失といった、企業にとって深刻な問題を引き起こします。
本コラムでは、「なぜデータ品質が重要なのか?」「それをどう維持・管理するべきか?」という視点から、企業成長に直結するデータガバナンスの考え方と実践方法をわかりやすく解説します。
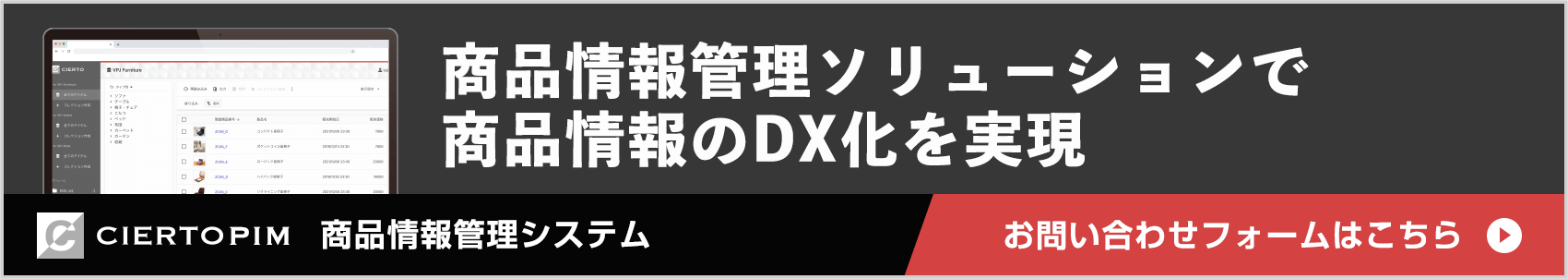
1. なぜ今“データ品質”が経営課題として注目されているのか?
1-1. データ活用時代に増える“情報の質”への懸念
マーケティング、営業、EC、サプライチェーンなど、企業活動のあらゆる場面でデータ活用が進む中、「情報の正確さ・一貫性」がこれまで以上に求められています。 顧客属性や行動履歴といったパーソナルデータだけでなく、製品スペック、価格、在庫、販促情報など、日々扱う情報の量と種類は増え続けています。
一方で、それらの情報が正しく管理されていないケースも多く見受けられます。例えば、複数の部門が別々にデータを更新していたり、Excelや個人フォルダに情報が分散していたりといった状況です。こうした状態では、データの“鮮度”や“整合性”を保つのが困難になります。
1-2. 品質の低いデータが引き起こすビジネスリスクとは?
品質の低いデータ、すなわち「誤っている」「古い」「重複している」「不完全である」データは、企業活動にさまざまなリスクをもたらします。たとえば、製品のサイズ情報にミスがあれば、ECサイトや営業資料、印刷カタログ、外部メディアにまでその誤りが波及します。結果として、顧客の不満やクレーム、返品対応のコストが増加し、ブランドイメージの毀損にもつながります。
また、マーケティングや経営判断の根拠となるデータが不正確な場合、的外れなキャンペーン施策や誤った在庫配分が起きる可能性もあります。こうした意思決定のミスは、“見えない損失”として積み重なり、長期的な業績悪化の要因になりかねません。さらに、データ品質が悪いことで社内の業務効率も低下します。間違いを都度確認・修正する「リカバリー作業」が常態化していれば、本来注力すべき戦略業務に時間を割くことができません。
つまり、データ品質の低さは、顧客体験・業績・業務効率という三方向から企業にダメージを与える、見逃せない経営課題なのです。このように、情報の正確性と整合性が損なわれると、部門間の信頼や連携も崩れていきます。一見地味に見える“データ整備”の問題が、実は企業の組織的パフォーマンスやブランド価値にまで影響する重大な要素なのです。したがって、データ品質の担保は全社横断で取り組むべき「経営課題」であり、部門ごとの“部分最適”では解決が難しいという認識が重要になります。
2. 売上・業績に直結する“データ品質の影響”とは?
2-1. 商品情報のミスで顧客を逃すパターン
ECサイトやデジタルカタログ上に掲載される製品情報は、顧客が商品を比較・検討し、購入へと至る重要な判断材料です。
しかし、サイズ、素材、カラー、型番、対応機種など、商品情報に誤りや漏れがあれば、顧客はそのブランドに対して不信感を抱き、購入を控える可能性が高くなります。
また、スペック誤記による返品・クレームが発生すれば、カスタマーサポートや倉庫部門にも余計な負荷がかかり、本来の売上機会を逸する“負の連鎖” が起こります。
近年では、商品情報の正確さは「購入前の顧客体験」の一部とみなされており、情報の信頼性=ブランドへの信頼と直結しています。競合他社が似た商品を正しく明快に伝えていれば、ユーザーは迷わずそちらに流れてしまうでしょう。
つまり、データ品質の低さは、見えないところで“売上減少の要因”として作用しているのです。
2-2. 顧客体験の低下とブランド毀損リスク
顧客は企業の提供する情報に対して、“一貫性”と“正確性”を無意識に求めています。たとえば、Webサイトには「発売中」と表示されているのに、ECサイトでは「入荷待ち」となっていた場合、どちらが正しいのか判断できず、顧客の信頼は一気に揺らぎます。
このような情報の食い違いや整合性の欠如は、ランド全体の信用力を損なう大きなリスクとなります。
また、商品情報に誤りがあるままプロモーションが展開された場合、企業は後になって訂正や謝罪を余儀なくされ、広告費や印刷費の無駄が発生するだけでなく、顧客との関係修復にも労力を割くことになります。
こうした一連のトラブルはSNSなどを通じて拡散される可能性もあり、企業のブランド価値を長期的に毀損する恐れすらあります。
ブランドは、単なるロゴやデザインだけでなく、「発信する情報の正しさ」でも形作られます。つまり、データ品質の管理は、企業のレピュテーションリスク対策としても欠かせないのです。
2-3. 正しい意思決定を妨げる“見えないコスト”
データ品質の低下は、日々の業務でじわじわと企業の意思決定に悪影響を及ぼします。
たとえば、在庫数が正確に反映されていないマスターデータをもとに発注判断をすれば、過剰在庫や機会損失が発生します。あるいは、市場分析の基盤となる販売実績データに重複や漏れがあれば、的確な戦略立案は不可能です。
こうした誤った判断は、表面的には「単なる判断ミス」に見えますが、原因を突き詰めると“元データの品質問題”に行き着くケースが少なくありません。
さらに、各部門が異なる情報をもとに業務を進めることで、認識のズレや手戻りが頻発し、社内での意思疎通や連携の精度が低下します。これにより、社内調整や修正対応にかかる時間が増え、業務効率も著しく悪化します。
このように、正しく整備されていないデータは、企業の“見えないコスト”として蓄積し、利益を圧迫していきます。
裏を返せば、データ品質を向上させることで、売上増加とコスト削減の両面からパフォーマンスを向上させることができるのです。
3. データガバナンスの本質とは何か?
3-1. データ品質を“保ち続ける”ための仕組み
データ品質の問題は、一度整備したからといって終わるものではありません。
むしろ本質的な課題は「整えた状態を、いかに継続的に保つか」にあります。日々の業務の中でデータは追加・修正・削除され、複数部門や外部パートナーが関与することで、常に変化し続けています。つまり、“品質の揺らぎ”をコントロールする仕組み=ガバナンスの設計が不可欠なのです。ここで重要なのは、単にマスターデータを更新するだけでなく、誰が・いつ・どのようなルールで情報を扱うのかを定義し、それが組織全体に共有されていることです。
どれだけ優れたデータ構造を持っていても、それを維持する運用フローがなければ、すぐに品質は崩れてしまいます。データガバナンスとは、まさにその「品質を保つ文化・仕組み」を企業内に根づかせるための中核的な考え方なのです。
3-2. ガバナンス=責任・ルール・フローの明確化
「ガバナンス」と聞くと、法令遵守や経営統制のような堅苦しい印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、データガバナンスの実態はもっと実務的で、「情報の管理ルールを明確にし、全体で共有すること」に他なりません。
たとえば、製品マスタの項目を誰が入力するのか、どの部門が承認を行うのか、修正履歴はどのように残すのか――こうした“小さなルールの積み重ね”が、ガバナンスの骨格となります。さらに、責任の所在が曖昧だと、エラーや情報の抜け漏れが発生しても「誰が直すのか」が不明になり、現場で混乱が起きます。
これを避けるためにも、各データ項目やプロセスに対する“責任者の明確化”と“役割分担”が極めて重要です。
ガバナンスは単なる仕組みではなく、「人と情報のつながりを可視化し、組織に秩序をもたらす設計図」として機能するべきものなのです。
3-3. 情報の“属人化”から“仕組み化”への転換
多くの企業では、特定の担当者に業務知識やデータ運用が集中し、その人がいなければ正しい情報が取得できない、という「属人化」の問題を抱えています。これは一見効率的に見えても、退職や異動、休職などが発生した際に重大な運用リスクとなり、業務の停滞や引き継ぎミスを引き起こします。
こうした属人依存の状態を脱却するためには、データ管理のルールを組織の「仕組み」として定着させることが必要です。具体的には、情報更新のフローを可視化し、マニュアル化し、さらにワークフローで統制をかけていくことが挙げられます。
システムとプロセスが融合することで、誰が操作しても同じ水準の品質が保たれ、「人に依存せず、仕組みに頼れる体制」が実現します。属人化から脱却するということは、“属人性のあるノウハウ”を“組織資産に昇華する”という進化そのものです。データガバナンスの実践は、まさにこの転換を推進するための要です。
4. よくある失敗と“ガバナンス不全”の兆候
4-1. Excel管理や部署ごとのバラバラな運用
多くの企業でよく見られるのが、Excelやスプレッドシートに依存したデータ管理です。情報を手軽に入力・加工できる反面、バージョン管理や更新履歴の追跡が難しく、複数のファイルが乱立することで整合性が保てなくなります。
さらに部署ごとに独自のテンプレートや命名規則を使っている場合、同じ製品情報であっても表記ゆれや重複が発生し、全社的な統一性が失われていきます。こうした「ローカル最適」な管理方法は、短期的には便利に感じられるかもしれませんが、データの信頼性・再利用性・拡張性という観点では著しく非効率です。
特に、部門間でデータの受け渡しや再利用が必要な場面では、都度確認や手修正が発生し、業務の属人化と非効率な作業が常態化します。これはまさに、ガバナンスが欠如している状態の典型的な兆候です。
4-2. 誰が何を管理するのか曖昧な状態
もう一つのよくある問題は、情報の管理責任が不明確なまま放置されていることです。
たとえば「製品スペックは商品企画部が入力」「販促用の説明文はマーケが作成」「在庫情報は物流部門が更新」など、部門ごとに管理対象が分かれていても、その連携ルールや承認フローが曖昧だと、データの整合性が簡単に崩れてしまいます。このような状態では、エラーや変更が発生したときに“誰が修正すべきか”が明確でないため、対応が遅れたり、ミスが放置される事態に陥りがちです。
また、部署間で責任の押し付け合いが発生し、修正対応が遅れた結果、顧客への誤情報配信につながってしまうケースもあります。
つまり、「データの責任者がいない」「業務フローが可視化されていない」という状況は、ガバナンス不全の最たる兆候であり、早急な是正が求められるポイントです。
4-3. 情報の更新遅れやバージョン違いによる混乱
製品情報や価格、キャンペーン内容など、頻繁に変更が発生するデータにおいて、「どれが最新版かわからない」という状態は、現場に大きな混乱をもたらします。これは、バージョン管理が適切に行われていない、またはシステム上でリアルタイムな共有ができていないことが原因であることがほとんどです。
たとえば、営業チームが古い価格表をもとに提案書を作成してしまい、契約直前に訂正が入って信頼を失ったり、販促チームが終了済みキャンペーンの情報を使って販促物を制作してしまったり……といったトラブルは、ガバナンスの欠如が引き起こす典型例です。情報更新の遅延や、正誤不明なデータが複数存在する状況は、業務品質を下げるだけでなく、組織全体のスピードと判断精度を奪ってしまいます。こうした課題を放置せず、仕組みとして“常に正しい情報にアクセスできる体制”を整備することが、真のガバナンス強化に直結します。
5. 理想的なデータ管理を実現する“PIM+ワークフロー”とは?
5-1. PIMで情報の一元管理と多チャネル展開を効率化
分散・属人化した製品情報を一元管理し、すべてのチャネルに対して正しく、タイムリーに届ける――この理想的な情報基盤を支えるのが、PIM(Product Information Management/製品情報管理)システムです。
PIMは、製品にまつわるスペック、価格、説明文、画像、動画などの情報を一元的に集約し、そこから各媒体(EC、カタログ、Web、取引先ポータルなど)に最適化して出力できる設計になっています。この仕組みにより、情報の登録・更新が1カ所で完結するため、表記ゆれや入力ミス、バージョン違いの発生を大幅に抑制できます。
また、チャネルごとのフォーマットや言語に合わせた出力にも対応しているため、グローバル展開や販促業務のスピードアップにも貢献します。PIMを導入することで、製品情報の一貫性と運用の効率化を同時に実現でき、ガバナンス強化における“基盤整備”として非常に有効です。
5-2. ワークフローで承認・更新のルールを標準化
情報を正しく蓄積するだけでは、品質は担保できません。
実務では「誰が・いつ・どんな手順で」情報を更新・承認するかを明確にし、ルールとしてシステムに組み込むことが求められます。ここで力を発揮するのが、ワークフロー機能の活用です。ワークフローを導入することで、たとえば「商品マスタの初期登録 → 商品企画の確認 → マーケティングの文言確認 → 品質管理の最終承認」といった業務プロセスを標準化し、担当者ごとの手戻りや属人対応を排除できます。また、ステータス管理や差戻し機能によって、情報の進捗状況や履歴が可視化され、ミスの発見や対応が迅速に行えるようになる点も大きなメリットです。
ルールを“人が守る”のではなく、“仕組みで守る”状態を作ることが、組織としての情報品質を安定させるカギとなります。ワークフローはその実現を支える、まさに“情報運用の司令塔”といえるでしょう。
5-3. 情報の信頼性とスピードを両立する運用体制へ
企業が情報を発信するスピードは、年々加速しています。特に販促やECの世界では、新商品の立ち上げ、キャンペーン対応、商品仕様変更など、短期間で大量の情報が更新されます。このスピード感に対応しつつ、なおかつ品質を落とさないためには、「一元化された情報管理」と「標準化された更新フロー」の両立が不可欠です。PIMとワークフローを連携させれば、「誰が何をどこまでやったか」「どの情報が最新か」が常に明確であり、社内外の関係者が“迷わず使える信頼できる情報”にアクセスできる環境が整います。
さらに、こうした体制は属人化を回避するだけでなく、部門横断でのコラボレーションを促進し、情報の流通スピードそのものを底上げする効果もあります。
理想的な情報運用とは、単に整理されたデータがある状態ではなく、常に正しい情報が正しいタイミングで、正しい人に届く運用の仕組みがあること。 その実現に向けて、PIMとワークフローは今、最も注目されるべき組み合わせなのです。
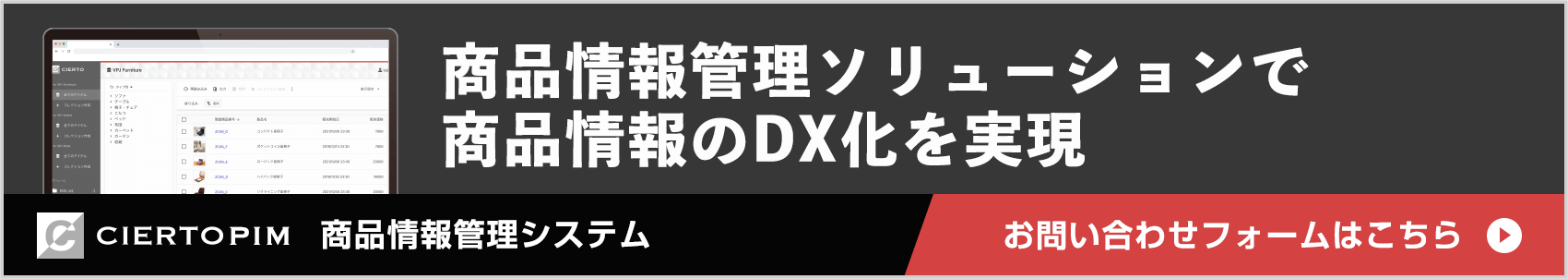
6. VPJが提供するCIERTOで実現する、実践的データガバナンス
6-1. 製品情報・素材・承認フローがすべてつながる統合設計
CIERTOは、VPJが提供するPIM・DAMを統合したデジタルコンテンツ統合管理プラットフォームです。
単なるデータベースではなく、「製品情報」と「クリエイティブ素材」、そして「運用プロセス(承認フロー)」までをひとつの基盤上で連携管理できるのが、CIERTO最大の特長です。例えば、商品情報に関連する画像・動画・取扱説明書といったコンテンツを、製品マスタと直接紐付けて管理することで、どの媒体に、どの素材が使われているかを正確に把握できる状態を実現します。また、修正が入った場合も、関連情報を横断的に確認・更新できるため、更新漏れや表記ゆれといったリスクも最小限に抑えられます。
さらに、CIERTOは柔軟な項目設計と権限管理が可能で、企業ごとの運用ルールに合わせたきめ細かな構築ができます。
データガバナンスの要となる「つながり」と「制御」を、現場で無理なく実践できる環境が整っています。
6-2. マーケ・営業・EC・制作部門が一気通貫で使える環境
CIERTOは、情報システム部門だけでなく、マーケティング、営業、商品企画、EC運営、クリエイティブ制作など、幅広い部門で“実際に使える”設計になっています。業務フローごとにダッシュボードや表示項目をカスタマイズでき、部門間の情報連携や共同作業がスムーズに進められるのが大きな強みです。たとえば、商品情報の登録は商品企画部が、販売説明文の作成はマーケ部が、バナー制作は制作会社が担当するような体制でも、CIERTO上で全員が同じ情報を見ながら、それぞれの作業を進められるため、やり取りの手間や伝達ミスが大幅に減少します。
また、外部の協力会社や制作パートナーともアクセス権を設定して安全に情報共有が可能で、データの一元管理と効率的な外部連携の両立が図れます。このようにCIERTOは、情報の正確性を担保しながら、業務スピードも落とさない、実践的な情報運用環境を提供します。
6-3. 複数業種への導入実績と支援体制で、安心の運用が可能に
CIERTOは、製造業、小売・流通業、出版、教育、金融、旅行業界など、さまざまな業種での導入実績があり、業種ごとに異なる情報管理の課題や運用フローに対応した豊富な知見を持っています。また、VPJでは導入時の設計支援だけでなく、運用開始後の活用アドバイスやカスタマイズ対応も含めた手厚いサポート体制を整えており、「導入して終わり」ではなく、「自社に定着するまでを見据えた導入」が可能です。
ガバナンス強化は、一朝一夕には実現しません。だからこそ、自社の業務や組織体制に寄り添い、継続的に伴走してくれるパートナー選びが重要です。CIERTOは、その“仕組み”と“支援”の両面から、企業のデータ品質向上とガバナンス定着を後押しします。
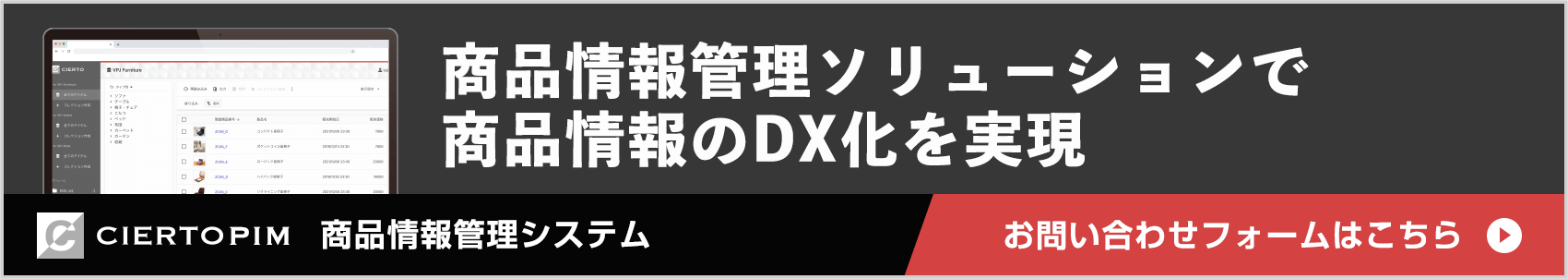
7. まとめ:データ品質とガバナンスが企業の“次の成長力”をつくる
企業のデジタル活用が進む今、「正しい情報を、正しいタイミングで、正しい形で届けること」は、もはや当たり前の前提条件です。
しかしその前提が崩れると、誤情報による顧客離れ、社内の混乱、業務の非効率、ブランドの毀損など、さまざまなかたちで企業活動にブレーキがかかります。このような状況を未然に防ぐためには、単なるデータ整備にとどまらず、それを継続的に維持・管理するための「ガバナンス」の仕組みが欠かせません。
その実現には、現場の運用ルールを明確にし、部門を超えて情報を連携し合える体制づくりと、それを支えるツール基盤が必要です。
VPJが提供するCIERTOは、製品情報・クリエイティブ素材・承認フローを一元的に管理できるプラットフォームとして、こうした“実践的なデータガバナンス”を現場レベルで実現する強力な選択肢です。
属人化や情報のばらつきから脱却し、信頼できる情報基盤のもとでスピードと品質を両立したいと考える企業にとって、CIERTOはまさに“次の成長力”を生み出す起点となるでしょう。
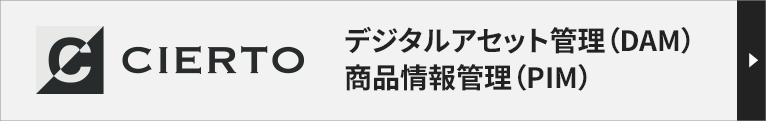
-

-
執筆者情報
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部です。マーケティングや商品、コンテンツ管理業務の効率化等について詳しく解説します。
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン について】
デジタルアセットマネジメント(DAM)を中核に、多様化するメディア(媒体)・コンテンツの制作・管理・配信環境を支援するITソリューションをご提案しています。